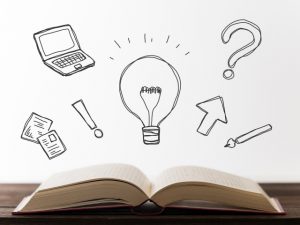漢文 詠嘆形《豈不用言(未然形)哉》での解釈
詠嘆形《豈不用言(未然形)哉》で、S.M君が素晴らしい解釈の提案をしてくれました!
出典は「寺師の漢文をはじめからていねいに」(東進ブックス) P172 練習問題11 問二
➃ 論事如此、豈不惑哉(『淮南子』)〔詠嘆で〕
◇読みは、「ことをろんずることかくのごとくんば、あにまどひならずや」
◇意味は、「そのように事を評するなんて、なんとうろたえる/迷うではないか」
取り敢えず出典の読みを正解と仮定すると、文中の【惑】の解釈として、
1.ハ行四段動詞「惑ふ」とすると、続く「なり」が断定の助動詞となり、読みが「まどふならずや」で矛盾。
2.ハ行上二段動詞「惑ふ」とすると、続く「なり」が断定の助動詞となり、読みが「まどふるならずや」で矛盾。
※仮に「なり」を伝聞・推定の助動詞とすると、この場合終止形接続なので、1と2共に読みが「まどふならずや」でやはり矛盾。
3.「なら」をラ行四段動詞「なる」の未然形と考えても、意味上不適切。
4.形容動詞「惑ひなり」とすると、続く「ず」が打消しの助動詞となり、読みが「まどひならずや」で合致。「いと惑ひなり」として、たいそううろたえる/迷うと訳せるので、形容動詞として適切。
S.M君は詳しく調べて、4の解釈を提案してくれました。
「なり」の識別で、形容動詞の活用語尾と捉えるのは、案外盲点をついているので要注意。
そこに気付いた点は、あっぱれ🎯
ところで、そもそももう一度この句形 詠嘆形《豈不用言(未然形)哉》の原点に立ち帰って考えてみると、読みは「あに…ならずや」と「あに…からずや」の二種類のみ。
そうすると、前者のように読む用言は形容動詞で、後者のように読む用言は形容詞しかないでしょう。
もし白文で出題されると句形の発見が厳しくなりますが、送り仮名があれば気付けると思います!
確かに「豈」の詠嘆形は上級レベルですが、文脈から疑問形や反語形に違和感を感じた時は、詠嘆形を当てはめてみると割り切って学習しておくのが、精神衛生上良いかも知れませんね。
但し、この句形の訳「なんと…ではないか」は、しっかりと覚えておきましょう!!
2021年9月30日 漢文授業より
難関大学/医学部/歯学部/薬学部/獣医学部受験なら
福岡市と北九州市が拠点のプロ家庭教師福岡
Enriched Academy 【エンリッチトアカデミー】